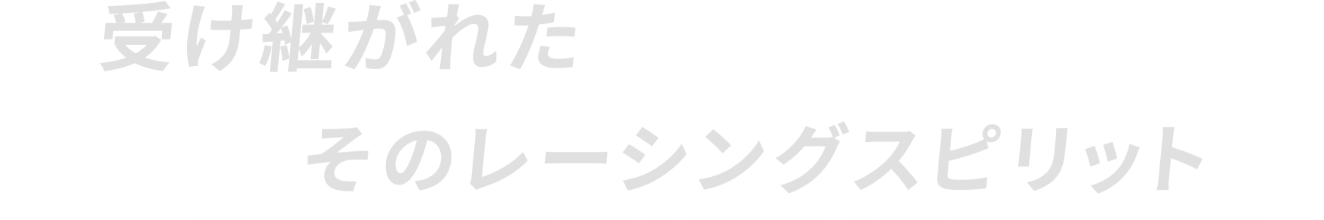Chapter.1革新と挑戦に
彩られた
栄光の日々
ルノー・スポールの
モータースポーツ史
Innovation &
Challenge

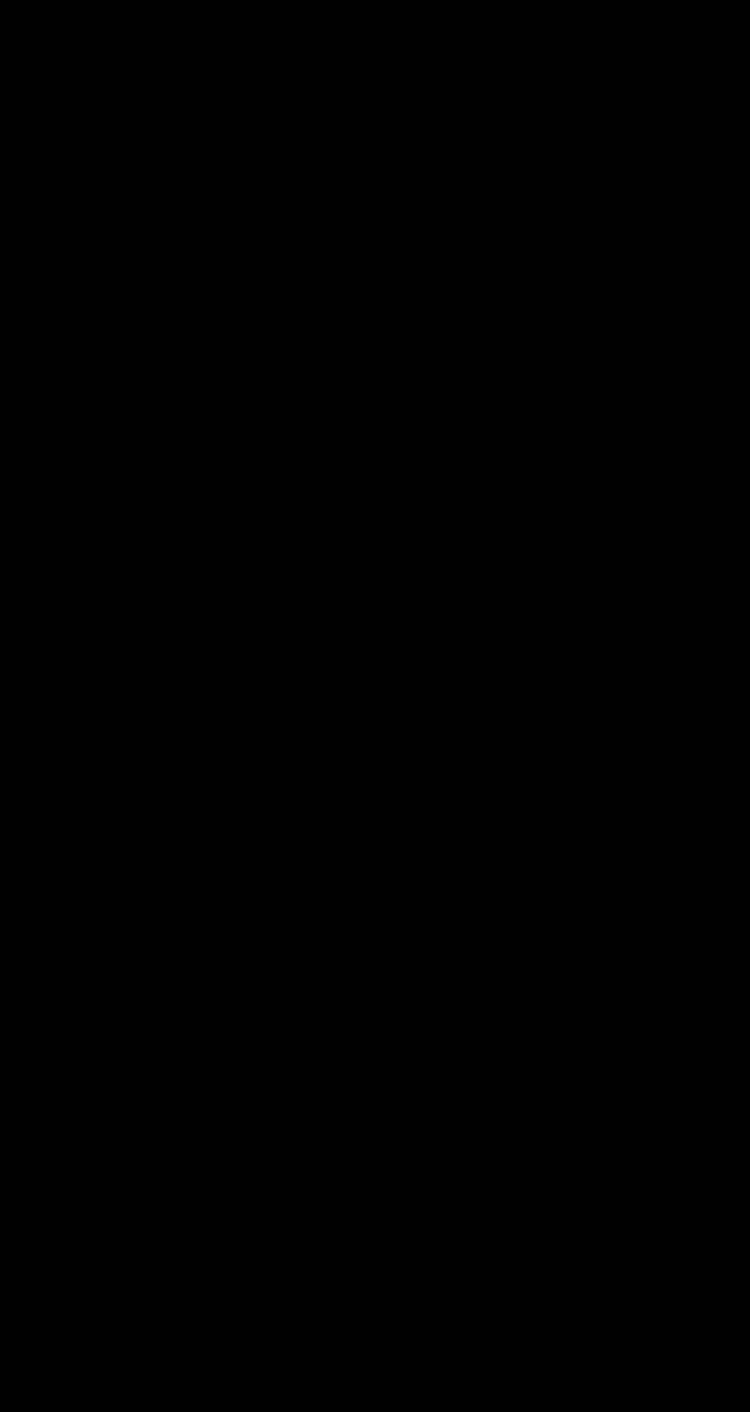



ルノー・スポールの歴史は、
サーキットやラリーでの活躍を抜きにして
語ることはできない。
ときに挫折に見舞われることはありながらも、常に革新的な技術と挑戦する姿勢によって
数多の勝利を掴んできた。
100年以上におよぶ、その栄光の足跡を
振り返ってみよう。
TEXT:世良耕太 (Sera Kota)
ストーリー一覧

- STORY.1GLORY DAYS OF
RACING1899年創業翌年からレースに参戦 -
創業翌年からレースに参戦
黎明期の自動車メーカーにとっては規模の大小を問わず、レースに参戦するのは自然な流れだった。ルノーも例外ではなく、第1号車を完成させた翌年にはレースに参加している。1899年のことで、パリを起点に行なわれた都市間レースに参戦した。このレースでは、創業者のルイ・ルノー自身がステアリングを握っている。世界最初の自動車レースは94年のパリ〜ルーアンとされているので、ルノーは自動車レースの始まりとも歩調を合わせていたことになる。
当時は排気量を増やすことが、スピードを向上させる手っ取り早い手段として定着していた。1900年代に入ると、排気量が10ℓを超える車両が珍しくなくなっていた。ところがルノーは「小さな車両」を意味するヴォワチュレット・クラスに出場し、小兵力士が大型力士を打ち負かすような痛快な勝ちっぷりを見せつけた。02年のパリ〜ウィーンでは、10ℓオーバーの大排気量車がひしめくなかで、3.8ℓに満たない4気筒エンジンを積んだルノー14CVが総合優勝を果たす快挙を成し遂げている。
喜びも束の間、03年のパリ〜マドリードで悲劇が訪れる。ルイの兄、マルセルが事故死したのだ。このレースではマルセルのほかにもドライバーと見物人が多く亡くなったため、これをもって都市間レースは禁止され、以後は公道を閉鎖したサーキット(周回路)で行なわれることになった。
06年には、現在F1が掲げている「グランプリ」の名を初めて冠したレースがル・マンで開催された。排気量13ℓの4気筒エンジンを積んだルノー90CVは、2日間に掛けて行なわれた2ヒート制のレースで優勝し、初代グランプリ・ウイナーになった。
09年のニューヨーク24時間で35CVが優勝した後、ルノーはサーキットレースと距離を置き、20年代にはアフリカに目を向ける。
23年には2400㎞を走り抜き、世界で初めて自動車によるサハラ砂漠横断に成功。4年後の27年には総距離1万8000㎞を走り、アフリカ縦断を果たした。その後のラリーレイドの精神を先取りした行動だった。
ふたりの天才技術者の邂逅

アルピーヌの創始者であるジャン・レデレ(写真左)と、エンジンチューンの大家アメディ・ゴルディーニ(同右)。ふたりは密接な協力関係を築きながら、1960~70年代のモータースポーツにおいてルノーの名声を大いに高めることとなった。 第二次世界大戦後の47年、国営企業として再スタートを切ったルノーは4CVの販売を開始。父親からルノーの代理店を引き継いだジャン・レデレはディエップのガレージで小さなRR車を自らチューンし、フランス国内のラリーやレースに出場。
立て続けに好成績を収めた。後のアルピーヌである。
レデレは52年にル・マン24時間に初出場し17位で完走すると、54年にはミッレミリアに出場しクラス優勝を果たす。その後も4CVで活躍を続けたレデレは55年、4CVのシャシーにオリジナルのボディを被せ、アルピーヌA106ミッレミリアの名を与えて市販。
58年には「チューニングの魔術師」の異名をとるアメディ・ゴルディーニがチューンしたエンジンを積むA108を発売した。ここに、ルノーのモータースポーツ活動を支え、発展に貢献した役者がそろったことになる。
63年、ルノーの要請によりアルピーヌ社内にモータースポーツ部門が正式に設けられ、以後、ルノーのモータースポーツ活動を担うことになった。ルノーの財政的な支援が得られたこともあり、アルピーヌは市販車をベースにしたGTカーの開発と並行し、プロトタイプカーの開発に乗り出した。目指すは伝統のル・マン24時間である。
63年には早速M63と名づけたプロトタイプカーを開発。車両ミッドに996㏄直列4気筒自然吸気エンジンを搭載し、流麗な空力ボディを被せたM63はニュルブルクリンク1000㎞レースでクラス優勝を果たし、幸先のいいスタートを切った。ところがル・マン24時間では出走した3台がリタイアする苦汁をなめている。
64年になると、アルピーヌはフォーミュラレースに進出した。最高峰のF1に駒を進めるのはもう少し後で、F2とF3に進出し、着実に地固めを行なっていった。

1953年になると、4CVをベースにジョバンニ・ミケロッティのデザインによる流麗なアルミボディを架装した4CVスペシャルが登場。同年、レデレの地元であるディエップで開催されたラリーで優勝したほか、55年にはミッレミリアでクラス優勝を遂げた。 
1947年にデビューした4CVは、RRで秀逸なパッケージを実現していたが、軽量なボディと四輪独立懸架の足まわりを活かしてモータースポーツでも活躍。1952年には、レデレ自身が4CVとともにル・マンに出場し、17位で完走を果たした。
- STORY.2RALLY1973年世界ラリー選手権の
初代チャンピオン -
A110がラリーで大活躍

R8の基本コンポーネントをベースにクーペボディを組み合わせたA110は1963年登場。この美しきベルリネットはラリーシーンで長きにわたって活躍。欧州ラリー選手権を席巻後、73 年から始まったWRC(世界ラリー選手権)の開幕戦となったモンテカルロで表彰台を独占すると、その年のマニュファクチャラーズ王座を獲得した。 これらの活動と並行し、アルピーヌのルーツとなったGTカーの活動は活発に行なわれた。そして、A110という名車が生まれる。A108の後継として63年に誕生したA110は、翌年から主力に。鋼管バックボーンフレームのシャシー後端に小排気量の4気筒エンジンを載せ、やはり軽量なFRPのボディを被せた。RR(リヤエンジン・リヤ駆動)によるトラクション性能の良さと軽さを武器に、A110はラリーシーンでの存在感を強めていく。
69年限りでル・マンへの挑戦を一時休止したルノーとアルピーヌは、活動の軸足を完全にラリーに移した。その効果は71年に現れ、モンテカルロ、イタリア、オーストリアン・アルプス、アクロポリス、ジュネーブ、ポルトガルなどで優勝。圧倒的な強さを見せつけて年間タイトルを獲得した。
2年後の73年にはWRC(FIA世界ラリー選手権)が始まった。この年のアルピーヌA110も圧倒的に強く、開幕戦モンテカルロと最終戦ツール・ド・コルスで1〜3位を独占。ポルトガル、モロッコ、アクロポリス、サンレモでも優勝し、フィアット、フォード、ボルボ、サーブ、ダットサンなどの2位以下に大差をつけてWRCの初代チャンピオンになった。
この年、アルピーヌは自社株の55%をルノー公団に譲り渡し、名実ともにルノーの傘下に入った。これに伴い、レース活動の拠点はディエップからヴィリ・シャティヨンに移った。一旦は休止していたプロトタイプカーの開発も再開され、ゴルディーニがエンジンを開発。2.0ℓV6エンジンを搭載したアルピーヌ・ルノーA440をサーキットに送り出した。

1964年、“ル・ソルシエル(魔術師)”の異名をとるゴルディーニが手掛けたR8ゴルディーニがデビュー。半球形燃焼室をもつ新型ヘッドやソレックス製ツインキャブレターの採用により、ノーマルの40㎰から95㎰まで出力を向上させた。64年から3年連続でコルシカラリー制覇の偉業を成し遂げる。 
当時のWRCの最高峰クラスであるグループ4に照準を合わせ、1.4ℓターボエンジンをリヤミッドに搭載した5ターボ。1981年のモンテカルロで名手J.ラニョッティが初優勝をもたらす。85年には1.5ℓに排気量を拡大したマキシ5ターボに進化。
- STORY.3LE MANS
24 HOURS悲願だった総合優勝を果たす -
ル・マン制覇、そしてF1へ

1973年にアルピーヌはルノー傘下となり、同年からアルピーヌ・ルノーA440でスポーツカーレースに復帰。76年に2.0ℓV6ターボを搭載したA442を登場させた後、78年にはその進化版であるA442Bがル・マン初制覇の宿願を果たすこととなった。 翌75年、ルノーはル・マン必勝を期し、革新的な技術をレースシーンに持ち込む。過給機の一種であるターボチャージャーだ。航空機用エンジンの技術として知られていたターボをレースの世界にも導入することで、自然吸気エンジンでは実現しえない高出力を得て対他競争力を高める考えだった。
76年、アルピーヌは完全にルノーに吸収され、以後、モータースポーツ活動はルノー・スポールの名の下に行なうことになった。78年、ルノーは4台のワークスマシンをル・マンに投入すると、2.0ℓV6ターボエンジンを搭載するD・ピローニ/J-P・ジョッソー組のA442Bがポルシェ936との激闘を制し、悲願のル・マン24時間初優勝を果たした。この快挙を潮時に、ルノーは再びル・マンから距離を置く。
それはF1に集中するためだ。当時のF1は3.0ℓV8自然吸気のコスワースDFVが席巻。規則上は1.5ℓターボを選択することも可能だったが、信頼性が確立されておらず、複雑な機構をもつがゆえに制御に困難が予想されるユニットに手を出す者などいなかった。ルノーはターボエンジンの将来性に懸け、リスクを承知でターボに手を出した。
エンジンはA442用の2.0ℓV6をスケールダウンした1.5ℓV6で、ゴルディーニによって開発が進められた。ルノーがRS01を引っ提げてF1に初参戦した77年当時、エンジンだけでなくシャシーも自前で開発するワークスチームはイタリアのフェラーリとイギリスのBRMだけだった。誰も見向きもしなかったターボエンジンを選択しただけでなく、シャシーも自前で開発するなど、見ようによっては無謀な取り組みだったが、ルノーは本気でF1に革命を起こそうとしていた。革命的だったのはタイヤにも言え、同郷フランスのミシュランを選択。ラジアルタイヤをF1に初めて持ち込んだ。燃料はエルフ、ドライバーはJ-P・ジャブイーユで、オールフランス体制での参戦だった。

ル・マン24時間レースにも積極的だったアルピーヌは、総合優勝を狙って1963年にプロトタイプカーのM23を投入。68年にはゴルディーニ設計の3.0ℓV8エンジンを搭載したA220(写真)で必勝を誓ったものの果たせず。この年を最後に、アルピーヌはしばらくル・マンから姿を消すこととなる。
- STORY.4FORMULA 1最高峰に数々の革命をもたらす
-
ターボでF1初優勝の快挙

ル・マンの次に目指すは、F1の頂点。ルノーはエンジンのみならずシャシーも自社で製作したRS01で1977年のグランプリに登場。当初、信頼性不足に泣かされた1.5ℓターボエンジンは徐々に熟成が図られ、79年に地元のフランスで優勝。
これはルノーのみならず、ターボエンジンにとっても初の栄誉であった。参戦当初はエンジントラブルが頻発し、ルノーのコーポレートカラーであるイエローの車体から白煙を吹き出したことから、「イエローティーポット」とありがたくないニックネームで呼ばれることにもなった。しかし、不断の開発によって信頼性が徐々に確立されると、パフォーマンスが際立つようになった。そして79年、シングルターボからツインターボへと進化したルノー・ゴルディーニEF1を搭載したRS10は、ジャブイーユのドライブにより、地元フランスGPでF1初優勝を果たす。ルノーのこの勝利は、80年代にピークを迎えるターボエンジン時代の幕開けだった。
81年には新進気鋭のA・プロストが加入。83年は4勝を挙げたプロストがシーズン終盤までチャンピオンシップをリードしたが、最終戦で逆転を許し、わずか2ポイント差でタイトルを逃す。コンストラクターズ選手権もフェラーリにおよばず、2位に終わった。ルノーはワークスチームとしてのF1活動を85年シーズン限りで終了。86年はA・セナらを擁するロータスを含む三つのチームにエンジンを供給するエンジンサプライヤーとして活動。この年限りで一旦F1から離れた。
86年に投入した1.5ℓV6ツインターボのEF15は、その後のF1エンジンのスタンダードとなる技術を搭載していた。ニューマチックバルブリターンシステム(NVRS)である。カムによって燃焼室側に押し出された吸排気バルブは、通常、金属製のばねの反力で元の位置に戻る。ところが高回転化していくとバルブの速い動きにばねが追従できなくなってしまう。そこで、空気の反発力を利用してバルブを元の位置に戻すのがNVRSだ。ルノーが開発したこの革新的な技術は、高回転化が進んでいくF1エンジンにとって欠かせないものになった。

瞬く間にターボ時代が訪れたF1において、ルノーは他チームにもエンジンを供給。そのひとつがロータスで、若き日のA・セナがロータス97Tルノーを駆り1985年のポルトガルでGP初優勝を達成した。しかし、タイトル獲得には至らず、86年限りでF1を撤退。 
1992~97年まで、6年連続でコンストラクターズ王者に輝いたルノー。また、96年はD.ヒル、97年はJ.ヴィルヌーブ(写真)がドライバーズ王者も獲得するなど、まさに最強エンジンの名を欲しいままに。そして、97年をもって二度目のF1休止を宣言した。 
2002年から第二期ワークス活動を開始。翌年にはF.アロンソのドライブでワークスとしては1983年以来となる優勝を遂げると、3.0ℓV6エンジン時代最後の05年にアロンソが王者獲得。2.4ℓV8エンジン初年度となる06年もアロンソがシリーズを制覇した。 NA時代のF1を席巻
ルノーが火つけ役となったターボエンジンが88年限りで禁止され、89年から3.5ℓ自然吸気エンジンの使用が義務づけられるようになった。このタイミングに合わせてルノーはエンジンサプライヤーとしてF1に復帰。V8とV12が主流だった時代にV10エンジンを開発し、またもやトレンドを築いた。エンジン単体の性能が速さを決定づける時代は終わり、車体の一部としての機能、すなわち軽さやコンパクトさが求められる時代になっていた。ルノーの時代を先取りしたコンセプトは見事にはまり、ウイリアムズ、ベネトンとともに92年から97年まで6年連続でコンストラクターズ選手権を制し、黄金時代を築いた。
97年限りで再びF1から退くと、2002年には「100%ルノー」のキャッチフレーズを掲げてワークスチームとしてF1に復帰。エンジンは90度が定番だった状況で111度の超ワイドなバンク角を選択し、低重心化を極限まで追求した。この試みは必ずしも成功したとはいえなかったが、革新的な技術を積極的に導入するルノーのDNAは健在だった。
F・アロンソとG・フィジケラを擁した05年、ルノーは1977年のF1参戦後初めて、ワークスチームとしてコンストラクターズ、ドライバーズの両タイトルを獲得した。翌2006年にもダブルタイトルを獲得し連覇。10年シーズン限りでワークス参戦活動を終了すると、11年からは2.4ℓV8自然吸気エンジンの供給先であるレッドブルが13年まで4連覇を果たし、ルノー製エンジンの優秀性を示した。
14年にエンジンが1.6ℓV6ターボとなり、これに高出力のモーターを組み合わせるハイブリッドシステムになると、当初、ルノーはパワーユニットサプライヤーとしてF1に参戦。16年にはワークス体制に切り換えて参戦すると、21年からはアルピーヌF1チームとして活動を続けている。
モータースポーツという極限の環境で鍛えられた様々な技術と情熱が、今日では低燃費と走りの楽しさを両立させたルノー E-TECH フルハイブリッド・テクノロジー*など、革新的な技術に寄与した。そして、その中心的な役割を果たしてきたルノー・スポールのすべては再びアルピーヌに受け継がれ、更なる発展を目指している。
*輸入車唯一。JATO Dynamics 調べ(2023年 8月現在)
- STORY.5ルノー・スポールから
アルピーヌへ2024年から
ハイパーカークラス参戦 -

フランスのレーシングチーム、シグナテックとのコラボレーションで2014年からル・マン24時間のLMP2クラスに参戦を開始したアルピーヌ。16年にA460がクラス優勝を遂げ、WEC(世界耐久選手権)も制覇。21年からハイパーカークラスへとステップアップした。 ルノーは21年、グループのモータースポーツ活動を再構築し、「アルピーヌ」ブランドに統一することにした。ル・マン24時間をシリーズの一戦に含むWEC(FIA世界耐久選手権)には、15年からLMP2クラスに参戦。16年はル・マン24時間でクラス優勝を果たし、WECのクラスタイトルを獲得した。
23年はA470でLMP2クラスに参戦。24年にはA424を引っ提げ、最上位のハイパーカークラスに参戦することが発表されている。

2024年からWECのハイパーカークラスにニューマシンのA424でファクトリー参戦を予定。写真は2023年のル・マン24時間レース決勝前夜に公開されたプロトタイプ。エンジンはアルピーヌF1とも関係が深いメカクローム社の3.4ℓV6ターボを積む。
- STORY.6ONE MAKE RACEモータースポーツの
裾野を広げる -
レースの未来とともに

クリオ(日本名ルーテシア)を用いたワンメイクレース「クリオ・カップ」は1991年以来連綿と続けられている。また、クリオ ラリー5で争われる国内ラリー選手権では女性ドライバーのカテゴリーも設けるなど、支援活動の幅は広い。 ここまで自動車メーカーが主体的に参戦するワークス活動を中心にルノーのモータースポーツ活動を振り返ってきたが、若手ドライバー育成のためのプログラムや入門カテゴリーのサポートに力を入れているのが、ルノーのモータースポーツ活動のもうひとつの大きな側面だ。トップカテゴリーに参戦して技術力を磨き、ブランドの魅力を広くアピールするだけでなく、モータースポーツ全体の底上げを図るスタンスである。
ルノー・スポール・アカデミーを前身とするドライバー育成プログラムは、21年のモータースポーツ活動再構築に伴ない、アルピーヌ・アカデミーに名称を変えてプログラムは引き継がれている。才能ある若手ドライバーを発掘し、手塩に掛けて育ててスキルを高め、ゆくゆくはF1ドライバーにするのが狙いだ。もちろん、アルピーヌF1入りを果たすのが理想である。
入門フォーミュラとしてプロストなど数々の名ドライバーを育て上げたフォーミュラ・ルノーは、フォーミュラ・リージョナル・ヨーロピアン・チャンピオンシップ・バイ・アルピーヌ(FRECA)として現代にその精神が受け継がれている。
1966年にクーペR8ゴルディーニのワンメイクレースとして立ち上がり、レースエンスージアストのための入門カテゴリーとして機能しているクリオ・カップは、アルピーヌ・レーシングに運営の母体が変わりながらも、ヨーロッパを中心に多くの国で継続開催されている。応援する対象を提供するだけでなく、参加して楽しむ機会を提供するのがルノーの伝統だ。

若手レーシングドライバーの登竜門と言えるフォーミュラ・リージョナル・ヨーロピアン・チャンピオンシップ・バイ・アルピーヌ。ヨーロッパを転戦しながら全10戦・20レースで争われる。元F1ドライバー、E.フィッティパルディの息子であるフィッティパルディJr.(16歳!)も参戦するなど、世界各国の若きホープたちが鎬を削っている。
最後のルノー・スポールモデル